交通事故治療のこと、ご相談下さい!
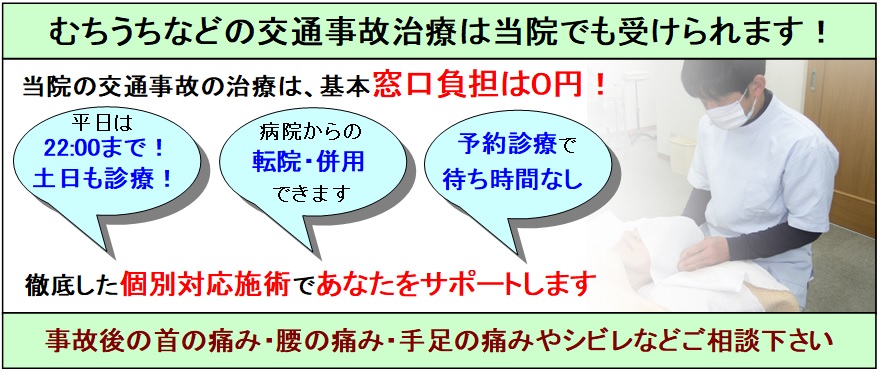
交通事故に関する豆知識
【自動車保険の基礎知識52】
〇むち打ち症の等級が低い時1
後遺障害の賠償(逸失利益)は、事故前の収入と障害の程度(後遺障害等級)によって
決まります。
むち打ち症の場合は、最近の傾向として低い等級で院呈されるケースが多くなっているようです。
【自動車保険の基礎知識51】
〇負傷箇所を再度怪我した時
裁判所の判例の傾向としては、過失割合認定をして賠償金を決めています。
つまり、1回目と2回目の事故の寄与率をそれぞれ定めて、
その割合に応じて損害を按分し、各加害者に賠償を命じるのです。
【自動車保険の基礎知識50】
〇治療費が120万円を超えたとき2
裁判や差押えなどの法的な手続きが行われた場合や、加害者が賠償責任を
認めた場合などには、時効の進行は中断します。
【自動車保険の基礎知識49】
〇治療費が120万円を超えたとき1
損害賠償の時効は3年です。これは、被害者が損害及び加害を知ってから3年という意味です。
ひき逃げの場合は、加害者がわかるまで時効は進行しません。
後遺症の場合は、医師が後遺障害が残った(症状固定)と診断した時からという事になります。
【自動車保険の基礎知識48】
〇示談が進まずお金に困ったら3
本請求は、仮渡金や内払金請求と区別するための通称であって、
自賠責保険本来の請求方法です。
【自動車保険の基礎知識47】
〇示談が進まずお金に困ったら2
内払金請求は、傷害事故特有の制度です。
治療が長引いて全部の損害額を決められない場合、既に確定した治療費や
休業損害等を10万円単位で請求できます。
なお、この請求は確定した損害額が10万円を超えることに、法定限度額120万円の範囲内で、
何度でも請求できます。
【自動車保険の基礎知識46】
〇示談が進まずお金に困ったら1
自賠責保険の被害者請求の方法には、仮渡金請求のほかに内払金請求と本請求があります。
【自動車保険の基礎知識45】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点10
保険会社が交渉相手なら、示談がまとまらなければ、(財)交通事故紛争処理センターに申し立てる
事もできますが、最終的には加害者と直接交渉する場合と同様、裁判所に調停を申し立てるか、
または訴訟を起こすことになります。
【自動車保険の基礎知識45】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点9
示談代行付の任意保険に加入していると、保険会社の社員が被害者と示談交渉を行います。
しかし、保険会社の対応は事務的で、その支払基準は弁護士会のそれより低い為、
不満を持つ被害者も少なくありません。
【自動車保険の基礎知識44】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点8
③調停・訴訟
どうしても示談がまとまらないときは、調停、訴訟などで解決することになります。
【自動車保険の基礎知識44】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点7
②相談所などの斡旋
日弁連の交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を頼めば、
無償で斡旋をしてくれます。
斡旋は被害者・加害者双方に希望あった場合に、早期に円満解決するように
当事者双方を援助するもので、中立・公正な立場で行われます。
【自動車保険の基礎知識43】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点6
何度交渉しても示談がまとまらないときは、次のような方法があります。
①弁護士に依頼
とりあえず交渉を打ち切り、弁護士に相談したり示談交渉を委任するのも一法です。
【自動車保険の基礎知識42】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点5
後遺障害がある場合、何級に該当するかが問題になる場合が多いものです。
しかし、結局は専門家の判断に任せるしかないでしょう。
【自動車保険の基礎知識41】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点4
慰謝料は精神的な打撃に対する賠償であるだけに、賠償額の算定は難しくなります。
一応の基準はありますが、折り合いがつかなければ訴訟によって決着をつけるしかありません。
【自動車保険の基礎知識40】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点3
示談交渉で問題となるのは次のような点です。
①収入証明の問題
自営業者などで年収について争いになる場合があります。
②過失割合の認定
過失割合でもめることが少なくありません。
事故が起きたら、事故状況のメモや証人になってくれる人を確保しておくことが大切です。
【自動車保険の基礎知識39】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点2
保険会社の交渉での心構えは
・恐れないこと
・冷静に交渉すること
・事前の準備を怠らないこと
・保険会社の言いなりにならないこと
要は納得がいくまで話し合い、疑問があれば率直に正すことです。
【自動車保険の基礎知識39】
〇保険会社と示談交渉するときの注意点1
保険会社の示談代行はその道のプロが担当しています。
示談交渉には次のようなメリットがあります。
・被害者が直接保険会社に請求できる
・交通事故の専門家が対応できる
・損害賠償問題を早く処理できる
・当事者同士では感情的になりやすいが、それを避けることができる
【自動車保険の基礎知識38】
〇死亡保険金はどう分けるか?2
死亡保険金は、死亡した保険金請求権を相続人が相続した結果受け取れるものだという
相続財産説と、保険契約に基づいて相続人が被保険者が死亡した時に
保険金を受け取れる権利をもともと持っていたという固有件説とがあります。
そこで、相続人は相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
【自動車保険の基礎知識37】
〇死亡保険金はどう分けるか?1
搭乗者傷害条項と自損事故条項のある自動車保険の加入者が、
交通事故で死亡すると、被害者の相続人には、死亡保険金が支払われることになっています。
もちろん免責事項のある場合は支払われません。
【自動車保険の基礎知識36】
〇任意保険の免責事由6
泥棒運転やハコ乗り運転の場合
搭乗者全員について保険金は支払われない(被害者は別)。
【自動車保険の基礎知識35】
〇任意保険の免責事由5
⑤自損事故条項・無保険車傷害条項・搭乗者傷害条項がセットされている場合で、
❶運転者の故意による事故、❷無免許運転、❸酒酔、麻薬等のため正常な運転ができない状況
のなかで起こした事故の場合
運転していた本人に対しては保険金は支払われない。
しかしそれ以外の搭乗者に対しては支払われる。
【自動車保険の基礎知識34】
〇任意保険の免責事由4
④運転者本人の損害(搭乗者保険がセットされていない)の場合
運転者本人は常に免責の対象となる。
また、車の所有者が家族とドライブに出かけ事故を起こしたような場合、
運転者本人はもとより、その車に乗っていた全員について保険金は支払われない。
【自動車保険の基礎知識33】
〇任意保険の免責事由3
③地震・噴火・台風・洪水などの大規模な自然災害の場合
このような場合の損害については、任意保険は支払われない
【自動車保険の基礎知識32】
〇任意保険の免責事由2
②運転者家族限定特約がある場合
この特約をつけると保険料は10%安くなる。但しこの特約がある場合に
家族以外の者に貸したりして事故が起きたときには、保険金は支払われない。
【自動車保険の基礎知識31】
〇任意保険の免責事由1
①運転年齢㉑歳未満不担保、あるいは26歳未満不担保の特約がある場合
この特約を付けると保険料は25~35%安くなる。
しかし、年齢未満の者に運転させ事故があると自賠責保険を超える額は全部負担することになる。
【自動車保険の基礎知識30】
〇保険金請求の時効
保険金請求権には時効があります。
時効が成立してから請求しても保険金は支払われません。
自賠責保険、任意保険ともに時効は2年です。
起算点は加害者請求は被害者に賠償金を支払った時、
被害者請求は事故発生の時です。
【自動車保険の基礎知識29】
〇自賠責保険の免責事由2
任意保険は自賠責保険に比べ、免責事項が多いの特徴です。
加入する前に、よく検討しておく必要があります。
【自動車保険の基礎知識28】
〇自賠責保険の免責事由2
①加害者及び加害車両の運行供用者が
②自分及び実際に運転していたものが無過失であり、被害者や第三者に故意・過失が
合ったことが証明でき、かつ
③加害車両に構造上の欠陥がなかったことが証明されると免責となります。
つまり、加害者(運行供用者)も保険会社も免責ということになります。
【自動車保険の基礎知識27】
〇自賠責保険の免責事由1
自賠責保険は被害者なるべく広く救済しようとする保険ですから、
免責事由は非常に制限されております。
まず、免責はないと考えてよいでしょう。
【自動車保険の基礎知識26】
〇保険金請求の手続き6
自動車損害賠償責任保険請求 提出書類一覧表
11.戸籍謄本
12.印鑑証明
13.診療費明細書
14.看護料、通院費、雑費等の立証書類
15.休業損害証明書、または税務署、市町村の発行する所得証明書
16.その他損害額を証明する資料
17.示談書
【自動車保険の基礎知識25】
〇保険金請求の手続き5
自動車損害賠償責任保険請求 提出書類一覧表
6.死体検案書、または死亡診断書
7.事故発生状況報告書
8.住民票、または戸籍抄本
9.委任状お曜日(委任者の)印鑑証明
10.被害者の領収書当加害者の支払いを証する書類
【自動車保険の基礎知識24】
〇保険金請求の手続き4
自動車損害賠償責任保険請求 提出書類一覧表
1.仮渡金支払請求書
2.保険金支払請求書
3.損害賠償額支払請求書
4.交通事故証明書
5.医師の診断書
【自動車保険の基礎知識23】
〇保険金請求の手続き3
保険金の請求は、加害車両が加入している自賠責保険の相談窓口です。
そのほか、自動車保険、自賠責保険の保険金の一括払制度もあります。
また、ひき逃げや加害車両が無保険車だったときは、政府に対し補償金の請求ができます。
【自動車保険の基礎知識22】
〇保険金請求の手続き2
示談交渉が長引いて、このままでは賠償金をもらえそうにない・・・
しかし、ケガなどの治療費などの支払いがかさんで、賠償金がないと生活が苦しい時、
賠償金がもらえるまでの自賠責保険の仮払金、内払金を請求することができます。
【自動車保険の基礎知識21】
〇保険金請求の手続き1
保険金は示談が成立して、加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に
請求するのが原則です。
【自動車保険の基礎知識20】
〇任意保険の種類と請求手続き5
②一括払い制度
加害者が自賠責保険のほかに任意の自動車保険(対人賠償保険)にも加入している場合には、
この保険の契約保険会社から自賠責保険を含め一括して保険金(損害賠償額)が支払われる制度
があります。この場合の手続きは任意保険の保険会社に相談することです。
【自動車保険の基礎知識19】
〇任意保険の種類と請求手続き4
自賠責保険と同様に加害者請求が原則ですが、被害者側が
直接請求する場合もあります。
①任意保険の内払い
任意保険には示談成立前の内払制度はありませんが、実際には治療費・休業損害などについて、
実損額を予測しながら内払金を支払っているようです。
【自動車保険の基礎知識18】
〇任意保険の種類と請求手続き3
また、保険会社の多くが売り出している各種の保険をセットにした総合保険として、
自家用自動車総合保険があります。
この保険に加入していると、示談代行、他車運転危険担保制度なども利用できます。
【自動車保険の基礎知識17】
〇任意保険の種類と請求手続き2
任意保険は自賠責保険では補いきれない部分を補償する保険です。
契約した保険の内容によって、さまざまな補償を受けることができます。
・車両保険金額:自分のクルマに破損が生じたときに支払われる保険です
・賠償保険:対人賠償保険と対物賠償保険とがあります。
対人保険は相手k型に人身損害があったとき、自賠責保険の限度分を超える分に対して
支払われます。対物保険は、相手方の物損(車両破損の修理代などに対して)
支払われます。
【自動車保険の基礎知識16】
〇任意保険の種類と請求手続き1
任意保険は契約によって、次のような事故の補償を受けることができます。
①対人賠償保険
②車両保険
③対物賠償保険
④無保険車傷害保険
⑤搭乗者傷害保険
⑥自損事故保険
【自動車保険の基礎知識15】
〇仮渡金額を区別する傷害の程度とは2
②仮渡金20万円(①を除く)
・脊柱の骨折
・上腕または前腕の骨折
・入院んが必要な障害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの
③仮渡金5万円(①②を除く)
・11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの
【自動車保険の基礎知識14】
〇仮渡金額を区別する傷害の程度とは1
傷害事故で請求できる仮渡金は被害者の傷の程度に応じて、3段階に分かれています。
①仮渡金40万円
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腿または下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上入院が必要な障害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
【自動車保険の基礎知識13】
〇自賠責保険の請求手続3
・仮渡金:死亡の場合 290万円 傷害の場合 程度に応じて40万円・20万円・5万円の3段階
・内払金:傷害事故で治療が長引き前部の損害額が決まらない場合で
損害が10万円を超える時、10万円単位で請求できます。
【自動車保険の基礎知識12】
〇自賠責保険の請求手続2
自賠責保険には被害者が事故によって困窮しないように、示談が成立して保険金が出るまでの
精度として内払金、仮渡金があります。
【自動車保険の基礎知識11】
〇自賠責保険の請求手続1
保険金とは加害者の損害賠償の支出を補償するものであり、
加害者請求が原則です。
しかし自賠責保険は被害者の保護のためにあり、被害者側からの請求が
認められています。
【自動車保険の基礎知識10】
〇自賠責保険の支払金額2
・死亡事故の場合:合計3000万円まで
・傷害事故の場合:合計120万円まで
・後遺症の残る事故の場合:
傷害事故の場合の限度額120万円のほか、後遺症の程度(1級~14級)に応じ、
3000万円~75万円まで
損害賠償がこれで足りない場合は、任意保険で補うことになります。
【自動車保険の基礎知識10】
〇自賠責保険の支払金額1
自賠責保険は、交通事故の被害者の最低限の補償を確保するためのものです。
したがって、支払い金額は一定限度までで打ち切られます。
【自動車保険の基礎知識9】
〇任意保険に加入しているのは2
やはり任意保険に加入しているのは安心です。
自賠責保険を超える倍書額は、任意保険から支払ってもらえます。
しかし、任意保険の普及率はそれほど高くありません。
【自動車保険の基礎知識8】
〇任意保険に加入しているのは1
自動車は、任意保険に加入していないと一般道路を走ることができません。
しかし、sの反面、運転者が死亡事故を起こしても、3000万円までの損害は
自賠責保険の保険金で補填されます。もっとも、最近の死亡事故では、
賠償額が1億円を超えることも珍しくありません。
【自動車保険の基礎知識7】
〇自賠責保険と任意保険7
※その他
①自賠責保険
・任意保険に比べ免責条項が少ない
・被害者の過失相殺、減額が制限される
・保険金の算出方法が定型化され迅速である
②任意保険
・自賠責保険と違い契約時に運転者を限定したり、保険会社が免責になる年齢を
指定したりすることがある
・自賠責保険に比べ免責条項が多い
【自動車保険の基礎知識6】
〇自賠責保険と任意保険6
※補償の意味
①自賠責保険:被害者の最低限の補償をかくほするためのものである
②任意保険:自賠責保険で足りない分を補填する保険である
【自動車保険の基礎知識5】
〇自賠責保険と任意保険5
※補償の範囲
①自賠責保険:対人賠償についてのみ、一定の額まで補償される
②任意保険:保険の種類、契約の仕方で、対人、対物、自損の補償がされる
【自動車保険の基礎知識4】
〇自賠責保険と任意保険4
※加入の仕方
①自賠責保険:自賠法によって車を所有する者は強制的に加入させられる
②任意保険:加入するかしないかは自由だが、多くの車の所有者が加入している
【自動車保険の基礎知識3】
〇自賠責保険と任意保険3
自賠責保険は、人身事故の被害者だけの舗装ですが、
保険金の算出方法が定型化され迅速、示談成立間の内払い、仮渡しなどの制度もあります。
任意保険は鍵者請求、示談成立後の支払いが原則ですが、契約の内容に応じ、
色々な態様の事故について補償します。
【自動車保険の基礎知識2】
〇自賠責保険と任意保険2
賠償金はまず
①自賠責保険
から支払われます。①で不足する場合は、
②任意保険
から契約の内容に応じて支払われます。それでもカバーできない場合は、
③加害者の自己負担
となります。
【自動車保険の基礎知識1】
〇自賠責保険と任意保険1
自賠責保険は被害者の最低限の補償を確保するための強制保険、
任意保険は自賠責保険では補いきれない部分を補償する保険です。
【損害賠償額の具体的な算定例19】
物損事故の算定例4
〇代車使用料
車両の使用態様により相当な修理期間に限り認められます。
〇その他
事故当時の着衣(洋服・下着など)のほか、場合によっては腕時計、ネックレス、万年筆、
メガネなどはもとより、自転車、自動車、家屋などの損傷にまで及ぶことがあります。
※物損事故の賠償額の算式
物損事故の賠償額=修理費(修理不能の場合は物の価格)+評価損+代車使用料+
その他(事故で破損した衣料、メガネ、時計代など)
【損害賠償額の具体的な算定例18】
物損事故の算定例3
〇修理費
修理費が破損前の時価を超える場合又は全損の場合は、時価額
〇評価額
修理しても車両価格が下落する(格落ち)する場合には認められます。
【損害賠償額の具体的な算定例17】
物損事故の算定例2
車種、年式、肩が同一で使用状態や走行距離が同程度の車の中古市場の価格がわかれば
その価格ですが、中古市場における価格が明らかでない場合は、
定率法または定額法で算定します。
そのほか、車に積んでいた商品などの損害があれば、それも請求できます。
【損害賠償額の具体的な算定例16】
物損事故の算定例1
車対車の事故の場合、被害者側の車両の賠償については、
たとえ数か月の使用でも新車でないのですから、中古車として価格を賠償請求することになります。
問題は中古価格をいかに決めるかです。
【損害賠償額の具体的な算定例15】
後遺障害についての逸失利益、慰謝料の算定は、
後遺障害の程度を認定する後遺障害等級を基に行われます。
後遺障害についての慰謝料も後遺障害等級によって基準があり、これを基に考慮して
決められているようです。
【損害賠償額の具体的な算定例14】
後遺症のある傷害事故の場合は、事故直後の入通院についての損害賠償と
後遺症についての損害賠償を合わせて請求することになります。
〇事故直後の入通院についての損害賠償
・積極損害
・休業損害
・入通院について慰謝料
上記についかするかたちで
〇後遺障害についての損害賠償
・逸失利益
・後遺障害についての慰謝料
【損害賠償額の具体的な算定例13】
傷害事故で後遺症が無い場合2
②消極損害
事故前の収入(労働対価である収入)を基礎として、休業により現実に喪失した
収入を算定します。家事従事者などは、平均賃金を基礎として算定します。
③慰謝料
傷害の態様、実治療日数その他を勘案して算定。判例から見ると、
入院1か月32~48蔓延、通院一か月16万円~24万円。
但し期間によって逓減します。
【損害賠償額の具体的な算定例12】
傷害事故で後遺症が無い場合1
①積極損害
・治療費:原則として実費全額
・介護費:職業的付添人に支払った金額。家族の付添は、入院1日あたり5000円~6500円程度。
通院付添の場合は1日あたり3000円~4000円程度
・諸雑費:入院中雑費として、1日あたり1200円~1400円
・入退院通院交通費:電車、バス代(タクシー代を認める場合もあります)
【損害賠償額の具体的な算定例11】
ライプニッツ式、ホフマン式とは3
被害者にとっては、ライプニッツ式は刺し効く中間利息が多くて大変不利で、ホフマン式を
適用した方が得になります。
どちらの方式を使っても構いませんが、一般的に
自賠責保険や弁護士会ではホフマン方式を使っているようです。
【損害賠償額の具体的な算定例10】
ライプニッツ式、ホフマン式とは2
中間利息を差し引く方法には、ライプニッツ式計算方法とホフマン式計算方法があります。
どのような違いがあるかというと、ライプニッツ式が複利方式なのに対し、
ホフマン式は単利方式です。
【損害賠償額の具体的な算定例9】
ライプニッツ式、ホフマン式とは1
被害者が死亡した場合、その逸失利益や将来もらうはずの退職金は
損害賠償額に算定されます。しかし、これは将来貰うものですから、
実際の賠償額は中間利息を引いて現在の価格に直さねばなりません。
【損害賠償額の具体的な算定例8】
死亡時の損害賠償額の算式
損害賠償額=(積極損害+消極損害+慰謝料)×(100ー過失割合)/100+弁護士費用
【損害賠償額の具体的な算定例7】
死亡事故の場合
〇過失相殺
・事故発生に関して被害者に過失があれば、過失の割合(%)に応じて減額になります。
〇弁護士費用(判決による場合)
・訴訟に要した言語氏費用のうち、判決で容認される賠償額の10%前後の割合で
認められることが多いようです。(但し、判決による場合)
【損害賠償額の具体的な算定例6】
死亡事故の場合
〇慰謝料分
・死亡者が一家の支柱の場合 2100万円~2700万円
・母親(妻)の場合(一家の支柱に準ずる人) 1900万円~2300万円
・その他の場合 1700万円~2100万円
程度で裁判所は認めています。
【損害賠償額の具体的な算定例5】
死亡事故の場合
〇消極損害4
・中間利息の控除
将来の収入を現在受け取るわけですから、その間に生ずるであろう利息をホフマン方式または
ライプニッツ方式により控除します。
就労可能年数に応じた数値表を利用して計算します。
【損害賠償額の具体的な算定例4】
死亡事故の場合
〇消極損害3
・生活費
死亡者が一家の支柱の場合年収の30~40%、その他の男子の場合50%、女子の場合30~40%を目安として
実情に応じて控除されます。
・就労可能年数
原則として67歳迄働くものとします。それ以上の年齢層の場合は、
平均余命の2分の1とします。
【損害賠償額の具体的な算定例3】
死亡事故の場合
〇消極損害2
・事故前の年収
事故前の死亡者の実際の年収を基礎とする場合と、統計による平均的年収を基礎とする場合とがありますが、
具体的事例に適した算定がなされます。
【損害賠償額の具体的な算定例2】
死亡事故の場合
〇消極損害1
生存していれば将来得られたはずの収入から、生活費など必要経費を差し引いた額が
認められます。
(算定方法):(事故前の年収ー生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ式係数
またはホフマン式係数
【損害賠償額の具体的な算定例1】
死亡事故の場合
〇積極損害
・葬儀費用
原則として100~130万円程度です。裁判所の傾向としては定額化されており、
細かい領収書などを示さなくても具体的な立証をせずに上記基準額を認めています。
香典返し・接待費・年供養量などは認められていません。
仏壇・墓碑などの購入費は、若干の加算が認められる場合があります。
【過失割合の認定20】
路上に寝転んで轢かれたものの過失割合は、基本的に容易に確認できるときは30%、
そうでないときは20%です。さらに夜間の場合は20%、幹線道路の場合は10%の過失が
加算されます。
一方で、加害者の側も前を見ないで発車したのですから、20%の過失が加算されます。
結局、加害者60、被害者40の過失割合になります。
【過失割合の認定19】
バックした車が子供を轢いた時2
一方、幼児の方も路上で遊んでいたのですから、ある程度の過失はあります。
基本割合に前述の条件を加味して考えると、加害者は90%くらいの過失となります。
ただ、警笛を鳴らしていたことが照明されれば、75%程度の過失になるでしょう。
【過失割合の認定18】
バックした車が子供を轢いた時1
バックで起こす事故では、基本的にバックした方に80%の過失があります。
加害者の過失は、更に後方不注意でのバックと急発進、住宅地での過失などがあり、
およそ20%加算されます。
【過失割合の認定17】
Uターン車に追突したとき1
Uターンをするには、他の車両の正常な交通を妨害しないことが絶対条件です。
転回車の過失は大きいですが、直進車も相手がウインカーを出したのに気づいていたのであれば、
減速しても良いはずです。
したがって、Uターン禁止場所での事故の場合、直進車のスピードオーバーなどを勘案すると、
転回車90。直進車10の過失割合とみることができます。
【過失割合の認定16】
黄信号で交差点に入ったときの事故1
直進車同士の出会いがしらの事故の場合、信号無視の過失割合は、
黄信号で直進した車両が20%、赤信号で直進した車両が80%です。
【過失割合の認定15】
直進車と右折車の交差点での事故2
直進車がスピードオーバーしている場合は、直進車の過失割合は10%加算されます。
さらいに、右折車も徐行を怠り(10%加算)、大型車であること(5%加算)で過失が
15%加算されます。
結局、直進車25%、右折車75%が過失割合になります。
【過失割合の認定⑭】
直進車と右折車の交差点での事故1
交差点での直進車と右折車の関係は、直進車優先です。
この関係で事故が起きた場合、直進車30、右折車70の過失割合となります。
【過失割合の認定⑬】
真夜中の交差点での事故2
信号無視の運転手に対しては全額損害賠償を請求できるので、
何とかして賠償してもらうことです。
但し、タクシー運転手にも過失があれば、共同不法行為であるから
双方に請求できます。
【過失割合の認定⑫】
真夜中の交差点での事故1
制限速度より10キロオーバー、真夜中であったのでタクシーの運転手は減速しないで、
そのまま直進したことから過失に問われたケースです。
最高裁判所はこの条件での衝突事故ではタクシー運転手の過失は問えないとの
判断を下しています。
【過失割合の認定⑪】
バイクが横断中の老人をはねたとき②
しかし、事故が起こったのが住宅街の狭い道路で、被害者は老人だった場合、
防御能力にかけているという点も考慮して20%減算し、
結局10%の過失になるという考えもあるでしょう。
【過失割合の認定⑩】
バイクが横断中の老人をはねたとき①
歩行者が交通事故に遭った時、歩行者の側も何処を歩いていたかによって過失ありと
される場合があります。
例えば、横断歩道から少し離れた「横断歩道付近」であった場合、
被害者の側に30%の過失があると思われます。
【過失割合の認定⑨】
主な過失割合(4輪車同士の事故)
◎転回車との事故
・直進車Aと転回車Bが転回中に衝突・・・・A:20%・B:80%
【過失割合の認定⑧】
主な過失割合(4輪車同士の事故)
◎交差点でのその他の事故
・同幅員で左折車Aと直進車B(ABとも減速せず)・・・・A:50%・B:50%
・同幅員で左折車Aと右折車B・・・・A:30%・B:70%
・右折車同士で左方車Aと右方車B(AB共に減速せず)・・・・A:40%・B:60%
・T字型交差点、直接路直進車Aと突き当り路(右)左折者右折車同・・・・A:20%・B:80%
【過失割合の認定⑦】
主な過失割合(4輪車同士の事故)
◎交差点での直進車と右折車の事故
・直進車A、右折車Bとも青信号での進入・・・・A:30%・B:70%
・直進車A黄、右折車B青で進入黄で右折・・・・A:70%・B:30%
・直進車A、右折車Bとも黄信号で進入・・・・A:40%・B:60%
【過失割合の認定⑥】
主な過失割合(4輪車同士の事故)
◎交差点での直進車同士の事故(青信号対赤信号など)
・青信号車Aと赤信号車B・・・・A:0%・B:100%
・黄信号車Aと赤信号車B・・・・A:20%・B:80%
・赤信号車Aと赤信号車B・・・・A:50%・B:50%
【過失割合の認定⑤】
主な過失割合(歩行者と4輪車の場合における歩行者の過失割合)
◎路上横臥者の事故(横臥者の過失割合)
・自動車からの事前発見が容易でない場合:30%
・自動車からの事前発見が容易な場合:20%
【過失割合の認定④】
主な過失割合(歩行者と4輪車の場合における歩行者の過失割合)
◎後退車による事故
・歩行者が後退中の車の直後を通行:0%
・直後通行以外:30%
【過失割合の認定③】
主な過失割合(歩行者と4輪車の場合における歩行者の過失割合)
◎横断歩道外での歩行者の事故
・横断禁止場所:30%
・信号機が設置されていない横断歩道の直近を通過:30%
・通常の道路上:20%
【過失割合の認定②】
主な過失割合(歩行者と4輪車の場合における歩行者の過失割合)
◎横断歩道での事故
・歩行者が青で横断開始、車が赤で横断歩道を通過:0%
・歩行者が黄で横断開始、車が赤で横断歩道を通過:10%
・歩行者が赤で横断開始、車が青で横断歩道を通過:70%
【過失割合の認定①】
過失相殺については過失割合の確定がなかなか難しく、最終的には裁判所で
決定してもらうしかないのが実情です。
しかし過去の判例を基に過失割合認定基準が発表され、最近では日弁連交通事故相談センターの
過失割合一覧表が一応の目安となっています。
【過失相殺と過失割合の認定5】
◎重大な過失とはどんなものか?②
・信号を無視して交差点に進入し衝突した場合
・追突された場合、被害者が駐停車禁止地区に違反して駐車していたなど、
正当な理由がなく急停車するなど過失がある場合
・被害者が中央線を越えて衝突した場合
なお、適用される相殺率は過失の程度に応じて一定で、
その中間の率は認めていません。
【過失相殺と過失割合の認定4】
◎重大な過失とはどんなものか?①
自賠責保険で過失相殺がてきようされるのは、被害者に重大な過失がある場合のみですが、
その査定上、重過失と認定される事故の類型は以下の通りです。
・信号を無視して横断した場合
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されている場所を横断した場合
・泥酔等で道路上で寝ていた場合
【過失相殺と過失割合の認定3】
◎被害者側の過失に多いケース
・歩行者と車両
信号無視/子供の飛び出し/路上横臥/後退車
・車同士
交差点での事故/センターオーバー/割り込みと衝突/転回車
・自転車と車両
左折車の巻き込み
【過失相殺と過失割合の認定2】
◎過失割合とはなにか
①死亡及び後遺症については、20%、30%、50%の過失相殺率が適用されます。
②後遺症をともなわない傷害事故については、20%の過失相殺率が適用されます。
※被害者に重大な過失がある場合には、強制保険(自賠責保険)でも減額されます。
※強制保険の金額を超える場合、過失の程度に応じて(過失相殺認定基準表)減額されます。
【過失相殺と過失割合の認定1】
◎過失割合とはなにか
交通事故の場合、加害者、被害者双方に過失のある場合が少なくありません。
そのようなときは、過去の割合に応じて賠償額が相殺されます。
その際に問題になるのは「過失割合」の認定です。
【物損についての損害賠償の内容6】
◎積み荷の損害も請求できるか3
積荷が破損するケースは珍しくないと思いますが、人身事故での賠償額や
破損した自動車の修理代などと比べると金額も少ないせいか、
裁判を起こしてまで争う例はあまり見当たらないのが実情です。
【物損についての損害賠償の内容5】
◎積み荷の損害も請求できるか2
積荷を売ったら上がったであろう利益までは、賠償の対象にはなりません。
また、壊れた積荷の一部に使える部品がある場合には、
その部分に相当する金額が当然、算定した賠償額から差し引かれます。
【物損についての損害賠償の内容4】
◎積み荷の損害も請求できるか1
積荷が壊れたり、価値がなくなったときの損害額は、原則として品物の時価です。
この時価てゃ、販売価格と卸売価格の二通りですが、再調達費用すなわち新しく商品を買うのに
要する費用です。卸売価格の場合は、かかった運搬費や包装費も時価に含まれます。
【物損についての損害賠償の内容3】
◎自動車以外の破損の場合
〇店舗などの破損
・建物の修理費
・物品の修理、交換費
・後片付け費用
・休業補償
などの合計が賠償額となる
〇電柱や塀の破損
新品の価格(新しく作る費用)を弁償しなくてはならない。
【物損についての損害賠償の内容2】
◎車の修理が可能の場合
修理可能の場合は、修理代が損害額になる。
但し、修理代が車の時価よりも高い時は、時価が損害額になる。
修理期間中の代車料、営業用の車なら休車損も、損害として認められる。
【物損についての損害賠償の内容1】
◎車が全損の場合
車の修理が技術的に不可能な場合、全損として事故時の車の時価が損害額になる。
ここでいう時価とは、同じ車を買い換えるのに要する費用のこと。
買い換えまでの代車料、営業用の車なら休車損も損害として認められる。
【消極損害はどのように算定するか23】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★失業者・無職者
無能力ゆえに会社を首になり、失業中の人については、被害者と同年齢の労働者の平均賃金を統計で
出すしかない。また、有能だが会社がつぶれて失業中の人については、失業前の収入を
基準としてよい(これを認めた判例もある)。
無職者であっても、労働の能力と意思を有していたものには逸失利益を認めるべきで、
逆に、働く意思のみられない利子生活者や浮浪者には認めるべきではない。
【消極損害はどのように算定するか22】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★芸能人・スポーツ選手
芸能人は公演などの契約に基づき収入額を算出
スポーツ選手は年棒制の場合は、過去3年間の平均収入によるとよい。
また、活躍年数が短いことも考えられ、先輩などの中から同程度の人を選んで
統計的に出すのも一法である。こうして算定した収入から経費、生活費を差し引く。
活躍できる年齢を過ぎた場合、賃金センサスの平均賃金で67歳までの収入を計算する。
【消極損害はどのように算定するか21】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★サービス業
収益の算出、純益の確定、本人の寄与率については、自営業者の場合と同様である。
売上、経費等に関する統計としては、総務庁「個人企業経済調査年報」の「サービス業の営業状況」がある。
【消極損害はどのように算定するか20】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★子供・学生《大学生》
勉強した専門で就職先が決まるのが普通なので、その行巣の大卒の賃金センサスが適用になる。
【消極損害はどのように算定するか19】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★子供・学生《高校生》
高校生が幼児と異なるのは、賃金センサス表の利用の際、幼児の場合は生産業労働者の総平均である
「学歴計」欄を用いるが、高校生の場合は「旧中・新高卒」該当蘭の数値を基礎収入として計算するので、
幼児より高めになる。
【消極損害はどのように算定するか18】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★子供・学生《幼児・小学生》
東京地裁民事交通部では、具体的に賃金センサスの平均賃金から生活費を50%控除し、
18歳~67歳までの49年間を終了可能期間とし、ライプニッツ方式による中間利息を控除する方法で
ほぼ統一されている。なお、養育費は控除されない。
【消極損害はどのように算定するか17】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★農業
収益を裏付ける帳簿などが無い場合がほとんどである。
作付面積によって、作物ごとに主産物、副産物などの
農産物売渡価格の中から、資本利子・地代と肥料費・種苗費、消毒防除費、水利費、
諸材料費、農機器蓄力比、労働費などを差し引き、
それに家族労働費を加えた原価計算方式などで算出する。
【消極損害はどのように算定するか16】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★主婦
判例によると、次の4つの方法がみられる。
①女子労働者の賃金センサスによる平均賃金を基礎とする
②家政婦の賃金を基礎とする
③家政婦の賃金と女子労働者の平均賃金の範囲内で相当額を認定する
④家族がが主婦の家事労働を得られなかったので、家政婦などの代替労働を雇い入れ、
このため財産上余分に支出した出費を基準とし具体的に認定する
この4つのうち、①の賃金センサスによる方法の算定が簡単で便利なので、
多く用いられているようである。
【消極損害はどのように算定するか15】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★自営業者
収入額を証明するものに、税務署に対する所得申告書がある。
実際はそれ以上の収入がある場合、その実収入額を証拠により証明できれば
認められることもある。しかし、収益や経費を出す手がかりがない場合、
一般の統計資料によることによる。
また、家族と一緒、あるいは従業員を雇っている場合は、
級よの程度を考慮し、本人の純利益を算出する。
【消極損害はどのように算定するか14】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★恩給生活者
これについては、被害者の推定余命年数いっぱいまで貰えるはずであった恩給や年金、
遺族扶助料を損害として請求できる。
但し、受給権喪失額から本人の生活費を控除するのが妥当である。
【消極損害はどのように算定するか13】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★自由業者
実際の収入が税務署へ申告した額よりも多い場合には、資料によりそのことを証明できれば
実額を認めてくれる場合もある。
なお、医師、弁護士などの場合、稼働年数が70歳までとされる場合がある。
【消極損害はどのように算定するか12】
◎逸失利益・休業損害の証明の仕方
★給与所得者
通常、サラリーマン(給与所得者)の収入は、本給のほかに諸手当、賞与など、
労働の対価として受け取る報酬である。
損害の対象となるのは、これに限るものではなく、昇給や退職金なども含まれる。
本給、諸手当、賞与は、源泉徴収票や賃金台帳により通所うは証明される。
なお、諸手当のうち交通費の支給額や自動車のガソリン代の支給などのように
所得の対象にならないものは、損害の中に含まれない。
【消極損害はどのように算定するか11】
◎後遺症はあるが逸失利益を認めない判決
通産省技官である被害者は、通院治療の結果身体障害等級14級に相当する腰部挫傷後遺症を
残して症状が固定した。
この後遺症の逸失利益について、東京高裁は労働能力の一部喪失の事実を損害ととらえ、
収入に格別減少が無くても損害額を評価算定すべきとして、労働の力2%を7年間喪失した認めた。
昭和56年12月22日の最高裁判決は、被害者の右下肢局部神経症状は多分に心因性によるもので、
機能障害や運動障害はなく、また給与面で格別不利益な取り扱いはなかったと認め、
後遺症の程度が軽微で仕事の性質上現在または将来の収入減が認められない場合は
労働力の一部喪失による財産上の損害を認める余地はないとして、
逸失利益を認めた控訴審判決を覆しました。
【消極損害はどのように算定するか10】
◎後遺症があっても減収が無い場合
後遺症があっても仕事に特に影響せず、
収入が減少することが無ければ、逸失利益は認められません。
【消極損害はどのように算定するか9】
◎むち打ち症の場合の逸失利益
むち打ち症の動労能力喪失率と、これをいつまで認めるかについては争いがあります。
裁判所は、むち打ち症についても定型化を図っています。
むち打ち症は一種の神経症として、何年か後には治るものとみなされています。
【消極損害はどのように算定するか8】
◎労働能力喪失年数の決め方
死亡の場合の就労可能年数の算出と同じです。
つまり原則として67歳までを就労可能年数とします。
◎年収
年収の算出方法も死亡の場合と同じです。
但し、死亡の場合は消費生活費を控除しましたが、後遺症の場合は控除しません。
【消極損害はどのように算定するか7】
◎労働能力喪失率の決め方
後遺障害等級が決まったら、労働能力喪失率がでます。
参考となる表はありますが、あくまで参考で、
裁判所では各自の職業や年齢を検討して決めます。
【消極損害はどのように算定するか6】
◎後遺症と将棋等級の認定
後遺障害等級は1級から14級まであります。
先ず、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出し、
後遺障害の認定を受けます。
※後遺症の症状が固定するまでに時間がかかることがあります。
症状固定以前については、休業損害として補償を請求することができます。
【消極損害はどのように算定するか5】
傷害事故で逸失利益が問題となるのは、後遺症が残った場合です。
後遺障害等級表の何級に該当するかで逸失利益の額も決まります。
①:後遺障害第何級になるかを決める
②:①をもとに労働能力喪失率を決める
③:年収に喪失力をかけると減収率が決まる
④:③にホフマン係数かライプニッツ係数をかける
【消極損害はどのように算定するか4】
被害者が実際に損害を受けなかった場合には補償をうけられません
(会社から給料が全額支給されていた場合などがありますが、この場合、
会社は加害者に丘陵部を請求することができます)。
つまり、被害者は自分の受けた損害の限度で損害を請求できるということです。
【消極損害はどのように算定するか3】
休業損害の算出法(傷害事故)2
◎農・漁業者
年収を出し、それを365日で割って1日当たりの賃金を出し、休業日数をかけて算出する。
◎幼児・生徒・主婦
主婦の場合は、女子労働者の平均賃金を基準にして算出する。
幼児、生徒などの場合は、働いた収入がないので休業補償はない。
【消極損害はどのように算定するか2】
休業損害の算出法(傷害事故)1
◎サラリーマン
給料を基に計算する。日給計算の場合には、1日の賃金んが1日の休業の補償分となる。
長期休業でボーナスに影響がある場合、その分も補償してもらえる。
◎自営業者・自由業者
年収(前年度の確定申告額)をもとに算出。これよりも実際の収入が多い場合には
帳簿や書類によって証明すればよい。
【消極損害はどのように算定するか1】
消極損害とは事故に遭わなければ被害者が得たであろう経済的な利益のことです。
消極損害の算定方法は、死亡事故の場合と傷害事故の場合とで違います。
※死亡事故
・逸失利益:事故によって得られなくなった、その後得られたであろう収入の推計
※傷害事故
・休業損害:交通事故で負傷し、入院や治療の為に働けなかった分の損害
【積極損害はどこまで認められるか5】
◎雑費
・入院中の雑費
入院中の諸雑費については、入院1日あたり1200円~1400円と定額化しています。
裁判所では領収書がなくても1300円前後は認められます。
それ以上かかった場合は、特に必要があったもの以外は認められません。
・通院中の雑費
領収書によって加害者へ請求します。
・通院交通費
加害者に請求できます。タクシー代については必要性がある場合に限り請求できます。
【積極損害はどこまで認められるか4】
◎医療関係・入通院費2
・将来の介護費
後遺障害がある場合、平均余命1日あたり5000円~6500円が認められます。
但し、後遺障害1級の人にしか認められません。
・その他の医療関係費
将来の医療費(手術することが確実視されている場合など)、義足、車いす代、住宅改造費、
医師に対する謝礼、家庭教師代などが認められます。
【積極損害はどこまで認められるか3】
◎医療関係・入通院費1
・入院費、通院費
原則として実費相当額。
特別室や個室などでなく、その病院の平均的な室料が基準になります。
・付添人費用
職業看護人は支払った実費。近親者の付添は
1日あたり5000円~6500円程度。通院1日につき3000円~4000円程度です。
【積極損害はどこまで認められるか2】
◎温泉治療は認められるか?
傷害事故にあった被害者の中には、傷害部位の治療の為、温泉を利用したりする人がいます。
被害者の積極損害のうち、医療関係費ついては原則そして実費が支払われますが、
この温泉治療費を認めるかどうかもめることも多いようです。
自賠責保険や任意保険の支払い基準には、温泉治療については医師が療養上必要と
認めた場合に限ると明記されています。
加害者や保険会社に温泉治療費を侵害をとして認めさせるには、
自分の判断だけではなく、
医師の指示に従い、診断書などをとっておくべきです。
【積極損害はどこまで認められるか1】
◎死亡事故の場合の積極損害
①死亡までの医療費など
事故から死亡までの間にかかった費用。入院費、付添人費用などがこれにあたります。
②葬儀関係費
葬儀そのものにかかった費用のほか、49日の表示の費用や仏壇購入費、墓碑建築費が
若干認められるケースもあり、100万円~130万円程度が一般的です。
香典返しなどの費用は認められません。
③雑費
入院中にかかった諸雑費、交通費などです。
【損害賠償額の算定の仕方2】
◎損害賠償額の算定を有利にするには2
収入額の聡明は、被害者側でしなければなりません。
そしてこの金額をいくらまで認めさせるかにより、その損害額の総額が大きくかわってくるのです。
一方、被害者の損害額がいくら大きくても、被害者側の過失割合が大きければ、
実際の賠償額はごくわずかという事もあります。
結局、収入額と過失割合をどれだけ有利に認めさせられるかが、損害賠償額算定のポイントなのです。
【損害賠償額の算定の仕方1】
◎損害賠償額の算定を有利にするには1
損害賠償額の算定でいちばん難しいのは、被害者の収入と過失割合の認定です。
弁護士会、自賠責保険、任意保険のどの基準でも、治療費や交通費はかかった実費ですし、
慰謝料や雑費、葬儀費はだいたい定額化されています。
しかし、逸失利益や休業損害は、被害者の収入額が基準です。
【損害賠償の基礎知識32】
◎加害者が免責されるのはどんなときか?4
※医療ミスで被害が拡大した場合
交通事故の被害者が病院で処置を受けたところ、医療ミスがあり、被害者は死亡してしまいました。
このように事故に医療ミスが加わった場合、①加害者と医療機関が共同で連帯して賠償責任を負う、
②それぞれの過失割合に応じて賠償責任を負う、という2つの考え方があります。
今のところ①が通例ですが、最近では②の判例も出てきています。
被害者にとっては①の方が有利です。
なぜなら②のように別々の責任を認定されると、一方が控訴した場合、
前額の賠償を受けられなくなってしまうからです。
【損害賠償の基礎知識31】
◎加害者が免責されるのはどんなときか?3
※因果関係が明確でない事故
事故直後、被害者は軽症であったにも関わらず、数か月後、脳溢血で死亡してしまいました。
被害者の遺族としては、交通事故が原因ではないかと考えたくなるものです。
事故の加害者に損害賠償責任を請求しましたが、加害者としては納得がいかないでしょう。
不法行為をした加害者が賠償責任を負うのは、加害行為と被害発生のあいだに
因果関係がある場合です。
それも、直接その原因から通常生じてくる結果についてであって、
これを「相当因果関係」といいます。
さて、この因果関係は非常に判定が難しいものの一つですが、
裁判になって加害者が賠償責任を免れた例はまれです。
前述のケースのような場合でも、一見無関係のようですが、裁判に持ち込まれた場合、
因果関係ありとして賠償責任を負わされる可能性は大きいと思われます。
【損害賠償の基礎知識30】
◎加害者が免責されるのはどんなときか?2
※双方が死亡した場合
加害者と被害者の双方が死亡してしまっても、それで賠償責任がない(免責)ということには
なりません。なぜなら相続があるからです。
加害者の相続人は損害賠償請求責任を、被害者の相続人は損害賠償請求権を
それぞれ相続します。
被害者の相続人は、加害者の相続人への損害賠償請求をすればよいのです。
その際、相続人であることを証明するために、戸籍謄本などが必要になります。
しかし、相続は放棄や限定承認(負債を整理して余りがでたら相続)ができるので、
加害者の相続人にそれをされると、どうにもなりません。
但し、自賠責保険の被害者請求はできるので、被害者の相続人であることを証明すれば
請求できます。
【損害賠償の基礎知識29】
◎加害者が免責されるのはどんなときか?
故意または過失により、他人の権利を侵害し、それにより相手に損害を与えた場合には、
加害者は被害者に対し、その損害を賠償する責任が生じます。
但し、過失の立証は、被害者側がしなければなりません。
しかし、交通事故などの場合、一般的な不法行為と同様に被害者側に立証責任を負わせることは、
正義・公平の観点から考えても、被害者に酷だといえます。
そこで、一定の場合に故意または過失の立証責任を、被害者から加害者に移行し、
加害者が事故の無過失を立証しない限り、賠償責任を負わせるという考え方が出てきました。
これを無過失責任といいます。
無過失責任を認めるのは、自賠法第3条のほか、民法の使用者責任や責任無能力者の監督責任などです。
【損害賠償の基礎知識28】
◎複数の凝る麻が人をはねた事故での加害者の責任
従業員が起こした事故について賠償をした使用者は、従業員に対して求償することができるのでしょうか?
先ず、損害賠償は事故に遭った被害者への補償ですから、使用者は当然、賠償をする責任があります。
問題は賠償が終わった後、直接の加害者である従業員に求償することができるかどうかですが、
求償は出来ないと考えるべきでしょう。そのような求償を無制限に認めると、
個人の負担が大きくなりすぎるわけで、それを防ぐために自賠責保険や任意保険の制度があるのです。
【損害賠償の基礎知識27】
◎盗難車が起こした事故と所有者の責任
盗まれた車が事故を起こした場合、事故を起こした泥棒が全責任を負うのが当然のように思われます。
しかし、車を盗まれたことについて所有者に落ち度はなかったか、つまり車を盗まれなければ事故が
起こる因果関係はなかったことになるわけで、所有者に落ち度がある場合は責任を負う事になります。
車の所有者がエンジンキーを外さず、制動装置を施さずに自動車から離れたのであれば、
盗まれても仕方がないわけで、所有者には被害者への賠償責任があります。
もちろん、管理に問題がなければ、泥棒が全責任を負うことになります。
【損害賠償の基礎知識26】 【損害賠償の基礎知識25】 【損害賠償の基礎知識24】 【損害賠償の基礎知識23】 【損害賠償の基礎知識㉒】 【損害賠償の基礎知識㉑】 【損害賠償の基礎知識⑳】 【損害賠償の基礎知識⑲】 【損害賠償の基礎知識⑱】 【損害賠償の基礎知識⑰】 【損害賠償の基礎知識⑯】 【損害賠償の基礎知識⑮】 【損害賠償の基礎知識⑭】 【損害賠償の基礎知識⑬】 【損害賠償の基礎知識⑫】 【損害賠償の基礎知識⑪】 【損害賠償の基礎知識⑩】 【損害賠償の基礎知識⑨】 【損害賠償の基礎知識⑧】 【損害賠償の基礎知識⑦】 【損害賠償の基礎知識⑥】 【損害賠償の基礎知識⑤】 【損害賠償の基礎知識④】 【損害賠償の基礎知識③】 【損害賠償の基礎知識②】 【損害賠償の基礎知識①】 【自動車保険の仕組み⑥】 【自動車保険の仕組み⑤】 【自動車保険の仕組み④】 【自動車保険の仕組み③】 【自動車保険の仕組み②】 【自動車保険の仕組み①】 【交通事故の紛争解決法③】 【交通事故の紛争解決法②】 【交通事故の紛争解決法①】 【自動車損害賠償保障法(自賠法)③】 【自動車損害賠償保障法(自賠法)②】 【自動車損害賠償保障法(自賠法)①】 【民法の不法行為責任(民法709条)②】 【民法の不法行為責任(民法709条)①】 【民事上の責任(損害賠償責任)③】 【民事上の責任(損害賠償責任)②】 【民事上の責任(損害賠償責任)①】 【刑事上の責任と行政上の責任2】 【刑事上の責任と行政上の責任1】 【道路交通法】 【自動車損害賠償保障法】 【交通事故と刑法の規定】 【交通事故と法律と責任】 【交通事故にあったら、被害者が注意すること3】 【交通事故にあったら、被害者が注意すること2】 【交通事故にあったら、被害者が注意すること1】 【交通事故を起こしたとき、必ず守ること3】 【交通事故を起こしたとき、必ず守ること2】 【交通事故を起こしたとき、必ず守ること1】 【事故の発生から解決まで2】 【事故の発生から解決まで1】 【事故を起こさないための注意と工夫】 【「過失相殺」について27】 【「過失相殺」について26】 【「過失相殺」について25】 【「過失相殺」について24】 【「過失相殺」について23】 【「過失相殺」について22】 【「過失相殺」について21】 【「過失相殺」について20】 【「過失相殺」について19】 【「過失相殺」について18】 【「過失相殺」について17】 【「過失相殺」について16】 【「過失相殺」について15】 【「過失相殺」について14】 【「過失相殺」について13】 【「過失相殺」について12】 【「過失相殺」について11】 【「過失相殺」について10】 【「過失相殺」について9】 【「過失相殺」について8】 【「過失相殺」について7】 【「過失相殺」について6】 【「過失相殺」について5】 【「過失相殺」について4】 【「過失相殺」について3】 【「過失相殺」について2】 【「過失相殺」について1】 【車以外の損害賠償はどこまで請求できる?③】 【車以外の損害賠償はどこまで請求できる?②】 【車以外の損害賠償はどこまで請求できる?①】 【修理期間中などに認められる損害賠償は?②】 【修理期間中などに認められる損害賠償は?①】 【車の修理費用はどこまで認められる?②】 【車の修理費用はどこまで認められる?①】 【物損事故で注すべきポイントは?②】 【物損事故で注すべきポイントは?①】 【示談後に出てきた後遺症の対処の方法は?②】 【示談後に出てきた後遺症の対処の方法は?①】 【「むち打ち症」は後遺症として認められる?②】 【「むち打ち症」は後遺症として認められる?①】 【後遺症で請求できる慰謝料の金額はいくら?2】 【後遺症で請求できる慰謝料の金額はいくら?1】 【後遺症による減収分はいくらまで請求できる?2】 【後遺症による減収分はいくらまで請求できる?1】 【後遺症の積極損害はいくらまで請求できる?2】 【後遺症の積極損害はいくらまで請求できる?1】 【後遺症での損害賠償の請求方法について4】 【後遺症での損害賠償の請求方法について3】 【後遺症での損害賠償の請求方法について2】 【後遺症での損害賠償の請求方法について1】 【傷害事故の慰謝料について】 【失業者や学生、アルバイトの「休業損害」について】 【個人事業主の「休業損害」について】 【専業主婦の「休業損害」について】
◎家族で働く会社の車の事故と会社の責任
家族単位で事業をしている零細企業では、私用目的の車も会社名義にしていることはよくある話です。
そうなると、たとえ仕事に使っていなくても、事故を起こしたときの使用目的が
プライベートなものであっても、会社に責任があります。
社員である家族はその車の運行供用者であり、損害賠償責任を負うことになります。
また車が個人名義になっていても、ときどき営業用の使いに出ていたとか、
ガソリン代や車庫代を会社の経費で払っていたりした場合は、
やはり会社に損害賠償の責任があることになります。
交通事故に関する豆知識
◎個人の車が通勤中に起こした事故と会社の責任
個人の車が通勤中に起こした事故の場合、事故を起こしたのは業務以外の時間であり、
しかも会社の車ではないことから、一見会社には責任が無さそうに見えます。
しかし実際には、会社にも責任があるとの判断を下した判例があります。
会社が責任を負うケースは、営業の仕事などで個人の車を仕事にもよく使用していたり
会社がガソリン代を負担していたりといったように、かなり濃密な関係が仕事と個人(車)の間に
認められたときです。
会社が責任を免れるのは、そういった関係が全く認められないときです。
◎会社の車の時間外無断運転中の事故と会社の責任
会社の業務に関する範囲での事故はもちろん、休業中の社員が会社の車を無断使用して
起こした事故でも、会社は賠償責任を免れません。
しかし、同じようなケースでも事故現場が著しく遠方であった場合は、
(外観上も)会社の業務には関係ないとして会社の責任は
問われないという判例があります。
但し、顧客へのサービスなどが目的で遠方まで車を飛ばしてた時の事故については、
会社の業務の範囲内とみられ、責任を負うことになるでしょう。
◎下請け会社の起こした事故と親会社の責任
元請会社と下請け会社の社員との間に雇用関係はないケースでも
①元請人に指揮監督権があった場合はもちろん
②下請人の被用者がした行為の結果が予見できた場合
③下請人の被用者に対して間接的に指揮監督権を保有している場合は、
すべて元請人に使用者責任を認め、元請人の責任を拡大しています
これはたとえ車の名義が下請会社にあっても同じです。
こうした元請会社の責任は重くこそなれ、軽くなることはありません。
◎子供は何歳から事故の責任を負うのか?②
判例は概ね11歳前後から問題とし、普通12~13歳ぐらいから責任能力を認めています。
この場合、親に直接責任がなく、あまりにも子供を無責任に放任していたとか、
道義的な責任を痛感して自発的に賠償義務を肩代わりするという以外、
親に損害賠償を請求するのは難しいでしょう。
一方、子供が被害者の場合、責任能力ではなく損害の発生を避けるのに必要な注意をするだけの能力
(事理弁識能力)が問題です。
これを2歳6か月の幼児にも認めています。
◎子供は何歳から事故の責任を負うのか?①
民法では、満20歳未満の未成年者は親権者など決定代理人の同意がないと、契約や結婚などの
法律行為ができません。
しかし、交通事故などの不法行為では、未成年者でも責任能力があるというのが原則です。
◎「運行供用者」の判断は微妙
誰が、どのような場合に運行供用者とされるのでしょうか。
例えば、車を盗まれてその車両が事故を起こしたとします。
車の所有者に運行供用者としての責任があるのでしょうか?
・所有者が車を降りるときに忘れずにキーを抜くなど、管理に過失がなかったにもかかわらず、
盗まれて事故を起こした場合、盗難車の所有者は損害賠償の責任を負うことはないでしょう。
・キーを付けたまま車を放置するなど、所有者に管理上の過失があり、盗難と事故の間との時間が
密接している場合は、運行供用者として所有者の責任が問われる傾向があるようです。
◎運行供用者となる場合
・自動車の所有者
・自動車を他人に貸した者
・従業員が会社の車を無断運転した場合の会社
・所有名義を妻に変えていた車を、夫が日常運転していた場合の夫
・レンタカーの貸主
・子会社が親会社に専属して業務を行っている場合の親会社 下請けと元請の
関係にある場合も同様
・家族間で、車の持ち主は子供でも維持費は親が負担している場合の親
・従業員の自動車を雇用主が業務用に使用させている場合の雇用主
※なお、運行供用者に該当するかどうかは、個別の事例につき
裁判例を参考に検討する必要があります。
◎運行供用者として責任を負う場合
運行供用者については、自賠責法3条に次のように規定されています。
「事故の為に自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または
身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」
◎交通事故では妻は他人か?
加害者は、被害者の損害を賠償しなければならないという不法行為の典型は、
加害者と被害者が他人同士の場合には当たり前のことです。
しかし、加害者が夫、被害者が妻というように、当事者が家族間の場合には
心情的にも損害賠償の請求をすることは稀でしょう。
しかし交通事故の場合には、過去の最高裁判決で「妻は他人」だと認められました。
これにより、夫が運転するする車に同乗中に死傷した妻は、運転した夫に損害賠償請求をすることが
認められ、保険会社に対して自賠責保険金(損害賠償額)を直接、被害者請求できることに
なりました。他の家族間の事故についても、考え方は同様です。
◎好意同乗者や配偶者が被害者の場合
車の所有者が友人など(好意同乗者)を乗せたときの事故の場合、
乗せてもらった者は賠償請求することができるが、一般の事故と同じような額は
請求できず減額となる。
◎配偶者が被害者の場合
配偶者も損害賠償請求ができる。しかしこれも一般の場合に比べ低い額になる。
◎加害者が死亡した時の責任
交通事故の加害者が、じこによって死亡してしまっている場合もあります。
そのような時は、加害者の相続人が損害賠償の責任を負うことになります。
つまり、被害者としては、まず第一順位の相続人を探して損害賠償の請求をすることになります。
◎損害賠償義務のある人
・事故を起こした運転者
事故を起こした運転者は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者として、
損害賠償義務がある(民法709条)
・事故を起こした運転者の使用者
使用者は、その議場を執行中の運転者が事故を起こして他人に損害を与えた場合、
その損害を賠償する責任がある(民法715条)
・運行供用者
自己の為に自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命、身体を害したときは
運行供用者として賠償する責任がある(自賠法3条)
好意で乗せた車で事故を起こし、それでその人にけがをさせてしまう場合があります。
このような時は、「好意同乗」といって、
賠償金の請求は認められていますが、過失相殺によって減額されるのが一般的です。
また、好意同乗は、運転者と同乗者の関係の程度(親族、友人、恋人、上肢)で微妙に違い、
同乗の目的事情でも違ってくるので、一定の基準といったものはありません。
交通事故の被害者が重傷者の時は、被害者が加害者に対し直接損害賠償の請求を
することができない場合があります。
このようなとき、被害者に代わって一定の近親者が代理人として請求をすることができます。
被害者が幼児の場合も、幼児には法律行為能力がありませんから、親権者(親など)
)が
法定代理人として請求をします。
最終的に示談交渉を委任するとしても、被害者本人に代わって法定代理人が、
弁護士に依頼するということになります。
禁治産宣告は、禁治産者本人やその配偶者、4親等内の親族、後見人、保佐人、または検察官の請求
により、家庭裁判所が決定します。
なお、後見人は家庭裁判所が決定しますが、夫婦の一方が禁治産者宣告を受けた場合には、
他方の配偶者が後見人となります。
・禁治産者とはなにか
禁治産者とは、精神的な障害があるために、自分の行為の結果について、
合理的な判断をする能力のない人をいいます。
禁治産者は、未成年と同様に、単独で法律行為ができません。
各種の契約をしたり、交通事故の被害者として損害賠償請求をするような場合には、
後見人が法廷代理人としてこれらの法律行為を行うことになります。
禁治産者が勝手にやった法律行為は、取り消されます(民法9条)。
・被害者が未成年者の場合
被害者が未成年者のときは、本人に法的手続きをとる行為能力がないため、親権者(親)が
法定代理人として請求することになります。
被害者が禁治産者の場合にも後見人が請求します。
・被害者が直接請求できない場合
被害者が死亡しなくても、死と同視できるような重大な後遺障害が残ったときは、
一定の近親者(父母・配偶者及び子)が法廷代理人として
損害賠償の請求をすることができます。
・配偶者、父母、子自身の慰謝料請求
被害者が死亡した場合、配偶者・父母・子は、相続による損賠賠償請求のほかに
自分自身の慰謝料を請求することができます。
なお、自賠責保険では内縁の妻にも被害者請求を認めていますが、
死亡した被害者に相続人がいるときにはトラブルになることも多く、
相続法上種々問題を含んでいます。
〇被害者が死亡した場合
・相続人からの賠償請求
被害者が死亡した場合、損害賠償の請求権は相続され、次の順位で相続人が請求することになります。
①子(胎児を含む)・孫など、直系卑属
②父母・祖父母など直系尊属
③兄弟姉妹またはその子
なお、配偶者はどの場合でも相続人になります。
〇格落ちとはどんなことをいうのか2
格落ち価格は、通常修理工場が査定しますが、だいたいのカンですから、
あまりあてにはなりません。
判例も、購入代金や事故直前の時価の1割、修理費のほぼ3割、修理費の5割を超えない範囲などと
分かれますが、おおぬね修理費の3割または事故直前の時価の1割程度とみるべきです。
〇格落ちとはどんなことをいうのか1
自動車は一度事故に遭うと、どんなに充分な修理をしたところで、その価格は
下落してしまいます。
これを格落ちとか、評価損と言います。
たとえば、事故に遭う前は時価150万円の自動車が、事故後修理を終えて、一見元の通りに
戻ったが、その車の時価は120万円になってしまったとすると、
この差30万円が格落ちです。
〇物損事故の場合
※車を破損させた場合
①全損:時価額(事故当時の中古額)が損害となります
②修理が可能:修理費が損害となります
③代車料:修理期間中の代車料が損害となります
④休車損害:緑ナンバーの営業車の場合には休業したことによる営業損も損害となります
⑤格落ち(評価損):修理代の3割程度が格落ちとして損害となる場合があります
〇傷害事故の場合
※傷害で後遺症が無い場合
・財産的損害:治療費/付添人費用/通院交通費/雑費/休業損害
・精神的損害:入通院治療に対する慰謝料
※後遺障害がある場合
・財産的損害:治療費/付添人費用/通院交通費/雑費/休業損害/後遺障害による逸失利益
・精神的損害:後遺障害についての慰謝料
〇死亡事故の場合
・財産的損害
①死亡するまでのケガによる損害
②葬儀費
③逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入
・精神的損害
④慰謝料:被害者及び遺族に対する慰謝料
任意保険加入のメリットのもうひとつは示談代行付きです。
これは任保険のうち、自家用自動車総合保険の加入者に対して適用されるもので、
事故を起こした加害者や運行供用者に代わって、保険会社が被害者と示談交渉をしてくれます。
ほとんどすべての場合に保険会社が示談交渉の席に出てきます。
もし示談が成立せず、裁判になったときでも、保険会社はその顧問弁護士を加害者側の代理人
として立てて、訴訟に応じます、その費用は保険会社持ちですから、
加害者にとっては便利です。
任意保険加入のメリットは、まず自賠責保険の保険金額を超える賠償部分を
補ってくれるということです。
また、自賠責保険の対象にならない物損や自損事故の損害も
補ってもらえます。
〇任意保険(保険会社による保険)
人身事故による村議あがくが自賠責保険の限度額を超えた場合、
例えば死亡による損害額が6000万円で、このうち自賠責保険で3000万円だけ
支払われたとき、残りの3000万円は加害者自身の負担になります。
また、物損事故や自分だけの過失で怪我をしたときには、
自賠責保険では補償されません。このような場合、任意保険に入っていれば、
契約の内容に応じた補償を受けることができます。
〇任意保険(保険会社による保険)
任意保険とは、保険会社が売り出している自動車保険のことです。
加入するかどうかは自由ですが、現在車を所有している人の多くが
加入しています。
〇強制保険(自賠責保険)②
自賠法によって、傷害事故では120万円、死亡事故では3000万円までは加害者の支払い能力を補償し、
被害者が賠償を受けられるようになっています。
〇強制保険(自賠責保険)①
自動車損害賠償法に基づき、車の持ち主は強制的にこの保険への加入が義務付けられています。
交通事故野被害者は、加害者に損害賠償を請求するわけですが、
加害者側に支払い能力が無ければしはらってもらえません。
被害者の最低限の補償を確保するための保険、それがこの保険です。
自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険と呼ばれています。
但し、自賠責保険は対人賠償に限られ、物損事故の補償はしません。
〇時効を中断するには
示談交渉が進展せず、時効完成の期間が迫っている場合などは、
請求権者は時効中断の手続きをとる必要があります。
手続きは、内容証明郵便で相手方に賠償を請求した後、
6か月以内に裁判上の請求(調停申し立て、訴訟提起)をすることで、
時効は中断されます。
〇損害賠償請求権の消滅時効
損害賠償を請求する権利は、
損害と損害を加えた者との双方を知ったときから3年間これを行使しないと、
事項にかかって消滅します。
但し、自賠責保険の被害者請求についての時効は2年です。
しかし、時効期間を経過すれば、直ちに行使できなくなるのではなく、
時効を援用(時効であることを主張)することによって時効が完成し、権利が消滅します。
また、損害と損害を加えた加害者が事故後20年間わからないまま経過すれば
(例えばひき逃げの場合)、請求権は消滅します。
①示談
まず話し合い(示談)で解決することが望ましいでしょう。
しかし、話し合いによる解決には限界がある場合があります。
②調停
示談がうまくいかず訴訟をさけるなら、民事調停による解決を図ります。
③訴訟
訴訟は紛争解決の最後の手段です。
〇運行供用者責任
自賠法では、賠償責任を直接の加害者だけでなく、そのクルマを支配している者にも
負わせています。
これによって、請求出来る範囲が広がり、被害者は損害賠償をとりやすくなりました。
※但し、自賠法が適用されるのは、傷害、脂肪など人身事故に限られます。
物損事故の場合は、民法不法行為責任で損害賠償を請求することになります。
〇無過失責任主義
自賠法の最大の特徴は、民法709条では被害者に背負わせていた故意・過失の立証責任を、
加害者が無過失を立証しなければならないとしたことです。
加害者が無過失を立証することは不可能に近く、被害者が損害賠償を摂りやすくなっています
「この法律は、自動車の運行によって生命または身体が害された場合における
損害賠償を補償する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、合わせて自動車運送の
健全な発達に資することを目的とする」(自賠法1条)
民法は明治29年制定。
当時は自動車のことなど考えもつきませんでした。
自動車事故が多発するようになった今日、事故の立証は面倒なので、
民法では被害者の保護が難しくなってきました。
そこで、昭和30年に自賠法が制定されたのです。
民法709条は「故意または過失により他人の権利を侵害した者は、
損害を賠償する責任がある」と定めています。
しかし、この規定では、加害者に故意・過失があったなどの照明は
被害者の方がしなくてはなりません。
また、加害者および使用者(民法715条)以外の責任を追及することはできません。
自賠法の最大の特徴は、「無過失責任主義」と「運行供用者責任」の2点です。
◎無過失責任主義
故意過失がないことを、加害者が立証しなければならない
◎運行供用者責任
運転者やその使用者だけでなく、運行供用者にも責任がある
※但し、自賠法は物損事故には適用されません。物損事故の場合は民法709条で請求することになります。
民法第709条は、交通事故に限らず民事上の不法行為一般の損害賠償責任について規定しています。
これに対し、自賠法は交通事故による人身事故の被害者の保護を目的に
特に設けられた法律です。
人身事故の場合、ほとんどが自賠法によって損害賠償請求が
行われています。
交通事故を起こすと刑事上の責任、行政上の責任のほか、民事上の責任を負うことになります。
民事上の責任とは、交通事故によって損害を受けた人へ損害を賠償する責任のことです。
交通事故を起こすと交通違反の時と同じように違反点数が課せられます。
違反点数が一定以上になると、免許の停止・取り消しの処分を受けます。
自動車を運転して死亡・傷害などの人身事故をおこすと、刑法211条の
業務上過失致死傷罪による刑事責任を問われることになります。
検察官の起訴により略式または正式な裁判にかけられ、5年以下の懲役または
50万円以下の罰金に処せられます。
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する
傷害の防止に資することを目的としています。
自動車を運転する人にとっては、最も関係の深い法律です。
この法律は、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における
損害賠償を補償する制度を確立することにより、
被害者の保護を図り、合わせて自動車運送の健全な発達に資することを目的としています。
交通事故で警報が適用されるのは、211条の「業務上過失致死傷罪」の規定です。
また、当然のことですが、車を用いて故意に人を轢き殺した場合には「殺人罪」(199条)に
処せられます。
交通事故と民法の規定
民法709条以下では、不法行為について定めています。
つまり、交通事故で被害者になった場合、この条文により損害賠償の請求をすることになるのです。
示談交渉や裁判で証拠となる領収書、診断書、写真などは大切に保管しておく必要があります。
事故については警察にちゃんと届けておかないと、事故証明は書いてもらえません。
また事故証明がないと、強制保険や任意保険の請求ができず、場合によっては事故に遭ったことを
照明できなくなることもあるので、注意が必要です。
必ず医師の診断をうけること。また、後日の損害賠償などの交渉で不利にならないよう
事故状況を確認し、目撃者があれば、住所・氏名を聞いて
後日証人になってくれるよう頼んでおくとよい。
お互いの住所・氏名・年齢・職業・車の番号・車の所有者、
契約保険会社などを運転免許証、車検証、相手の説明などで確認しておくこと必要。
警察への届け出
加害車両の運転者は、事故の処理が終わったら
日時、場所、負傷者の人数と程度・壊れたもの・その後の処置を
警察に届けなければならない。
危険防止の措置
事故現場は混乱する場合が多いので、第2、第3の事故防止のために車の誘導など
危険防止措置を講じなければならない。
但し事故車の移動は、後日争いの原因になることが多いので、
警察官が車ではそのままにしておいた方がよい。
負傷者の救護義務
人身傷害を伴なう場合、事故関係者は負傷者を病院に連れて行ったり、
110番、119番に電話するなど必要な救護活動をしなければならない。
また、応急手当法を心得ておくのも運転者の常識で、自動車教習所の課程にも
応急救護の受講が組み込まれている。
民事上の責任は損害賠償責任で、事故当事者間の示談交渉によって解決されるのが一般的です。
事故を起こしたら、60日以内に保険会社に通知をします。
保険金は、事故野当事者が請求しなければ支払われません。
保険金の請求には時効があります。
交通事故には、死亡事故、傷害事故、物損事故があります。
事故が発生したら、事故関係者は救護措置、危険防止措置、警察への届け出を行う義務があります。
事故野加害者は
①刑事上の責任
②行政上の責任
民事上の責任
の3つを負うことになります。
交通事故は「クルマ」「人」「環境」という3つの要素が副zつに絡み合って起こります。
この3つの要素が万全であれば、事故を起こす可能性はほとんどないわけですが、
どれか一つでも歯車が狂うと、時として大事故につながってしまうことがあるのです。
たとえば、ドライバーがいくら安全運転をしていても、
道路に大きな穴があいていれば事故は起こりますが、ブレーキが故障してしまった場合も
大事故につながります。
高速道路上での厳しい基準は、制限速度の高い高速道路にあっては当然だといえます。
同じような事故状況でも、一般道以上に大事故につながる危険性が
高いからにほかなりません。
また、高速道路の特質として、後続車への安全確保に対する配慮なども、
過失割合を確定する上での重要な要素となっています。
高速道路では、車の流れを阻害する行為については、一般道よりも過失割合がおおきくなります。
これは本線車道でのスムーズな車の流れを確保することが必要なためです。
例えば、先行車の急ブレーキが原因の追突事故では、一般道での過失割合に比べ、
バイクの場合で20%、車の場合で30%も先行車(急ブレーキ有)の過失割合が大きくなります。
それほど過失割合の基準が厳しくなっているのです。
高速道路と一般道を比較した場合、「通常は歩行者の横断がない」「制限速度が高い」
「整備がよい」などの点が大きく違います。
したがって、高速道路上の事故では、事故の類型や過失割合の基本も
一般道とは異なってきます。
事故状況にもよりますが、被害者が児童や老人の場合は、5~10%が基本となる過失割合から
減算されます。それとは逆に、酒酔い、わき見運転、二人乗りなど、自転車に著しい過失が
あった場合には、自転車の過失が10%加算されます。
自転車と車の事故で特徴的なのが、センターラインオーバーによる対向車同士の事故です。
車同士や、バイクとくるまのじこでは、センターラインオーバーをした車両に
100%の過失があったのに対し、自転車がセンターラインオーバーした場合の
過失割合は30%となっています。
自転車と車の事故で特徴的なのが、センターラインオーバーによる
対向車同士の事故です。
車同士や、バイクと車の事故では、センターラインオーバーした車両に100%の過失があったのに対し、
自転車がセンターラインオーバーした場合の過失割合は30%となっています。
直進する自転車の信号機が「赤」、直進または右折する車の信号機が「青」や「青矢印」を
表示していた時の事故は、自転車の過失割合が80~85%と、
車の過失割合を大幅に上回ります。
車に比べて弱い立場の自転車であっても、信号機のある交差点での事故では、
歩行者と同じく、事故発生時の信号機の表示が過失割合に大きく影響します。
自転車の過失割合の基本は、歩行者とバイクのほぼ中間と考えて差し支えないでしょう。
自転車の過失割合が車を大きく上回るのは、信号機のある交差点での事故のうち、
直進する自転車の信号機が「赤」、直進する車の新合金が「青」や「青矢印」を
表示していた時の事故です。
進行義のある交差点での直進車同士の出会頭の事故では、同条件の事故でも一方の信号機が
「黄」、一方が「赤」の場合で20%、ともに「赤」の場合でも10%、
バイクの過失割合が車より有利になります。
また、先行者の急ブレーキが原因の追突事故では、
同条件でもバイクの方が車より40%有利です(停止しにくいバイクの特性も考慮されています)。
このようにバイクが有利なのは、バイク(自動二輪、原動機付自転車)と車の事故の場合、
バイク側に人身損害が生じたことを前提とした過失割合が示されているためです。
したがって、両者ともに物損のみの場合などは、「車同士の事故」の表を準用した方が
妥当なケースが多いでしょう。
信号機のある交差点内の事故では、一方が赤信号、もう一方が青信号の場合には、
バイクか車かに関係なく、赤信号の車両に100%の過失が認められます。
センターラインオーバーによる対向車先導しの事故も同様で、
センターラインをオーバーした車両の過失が100%です。
バイクと車の事故では、同じ事故状況でも、バイクの過失割合が車同士の車の場合よりも
10~20%ほど有利になることが多いといえます。
道路幅がほぼ同じで、信号機のない交差点での直進車同士の事故では、
交差点進入時に減速したかどうかで20%も過失割合が変わってきます。
車同士の事故では、示談交渉を有利に進める意味でも、事故状況で過失割合が
大きく変わるケースがあることを知っておく必要があります。
信号機のある交差点での直進車同士の事故では、両方の信号機が「赤」を表示していた時の
過失割合はともに50%ずつです。このような場合、一方の車両が「黄」で、もう一方が「赤」
と判断された場合には、「赤」で進行していた車両の過失が80%となります。
センターラインオーバーによる対向車同士の事故や、一方が青信号の時に、赤信号で交差点に
進入してきた車との事故などは、加害者車両に100%の過失があるのは明白です。
しかし車同士の事故では、事故状況が複雑なケースが多く、示談交渉が決裂し、紛争に発展することも
少なくありません。事故状況を客観的に判断する材料が少ないような場合、
当事者双方が「相手車両の方に多くの過失がある」と感じるためです。
歩行者と車の事故では、歩行者の過失が100%というケースはほとんどありません。
たとえ歩行者の無理な横断による事故であっても、歩行者と接触した車にも過失(安全運転義務違反)が
あると判断されるためです。
なお、事故状況にもよりますが、被害者が児童や老人の場合は5~10%、幼児の場合は5~20%が
基本となる過失割合から減算されます。
同様に、住宅街や商店街など人の横断や通行の多い場所での事故は、
歩行者の過失が5~10%ほど減算されます。
歩行者と車の事故の多くは、車の過失が60~70%以上になるのが普通です。
但し、信号機のある交差点の横断歩道上、またはその直近では、
事故発生時の信号機の表示が過失割合に大きく影響します。
歩行者が「赤信号」で横断、車が「青信号」で交差点に進入した場合は、歩行者の過失が
70%と車の過失を大幅に上回ることになります。
「横断歩道上の事故なら歩行者に過失はない」とよく言われますが、
過失割合では常に歩行者優先というわけではないのです。
代表的な過失相殺基準には、
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部編)」
「交通事故損害額算定基準(日弁連交通事故相談センター専門委員会編)」
「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(
(東京地裁民事交通訴訟研究会編)」があります。
現在、裁判所や弁護士、保険会社では、裁判官や弁護士によって作成された過失相殺基準に
基づいて過失割合を決めています。
過失相殺基準では、「歩行者と車」「車同士」「バイクと車」「自転車と車」「高速道路上」
など、事故の類型ごとに過失割合の基本が定められており、事故の状況を
加味して過失割合を修正できるようになっています。
例えば、損害賠償額1000万円の事故の場合、過失割合10%の違いで100万円、20%の違いで200万円
というように、加害者にとっては支払う額、被害者にとっては受け取る額が大きく変わってきます。
それだけに過失割合の判定は非常に重要です。
一方、損益相殺されない主な利益としては、生命保険金、幼児の養育費、搭乗者傷害保険金、
傷害保険金、生活保護法による給付金、身体障碍者福祉法による給付金などがあります。
損益相殺される主な利益には、死亡事故での将来の生活費のほか、労災保険金、損害保険金、
加害者からの見舞金、自賠責保険金などがあります。
事故を原因とした利益を控除することを「損益相殺」といい、被害者にとって利益となる分は、
損益相殺によって損害賠償額から控除されます。
被害者の損害賠償額が減額されるのは、過失相殺だけとは限りません。
被害者が死亡した場合の逸失利益からは、将来の生活費が控除されます。
これは事故により被害者(遺族)が損害以上の利益を得るのを防ぐためのものです。
任意保険では、保険会社が被害者の過失を細かく査定し、被害者に普通の過失(軽過失)がある場合でも、
その過失割合を損害額から減額します。なお、加害者から被害者に支払われる保険金が先に
自賠責保険から支払われた場合で、被害者への損害賠償額が自賠責保険だけでは不足する場合に、
その不足分が任意保険から支払われることになります。
被害者にも過失がある場合、過失相殺されることによって損害賠償額は少なくなります。
この過失相殺の制度は、自動車保険でも適用されます。
但し、自賠責保険と任意保険ではこの適用範囲が異なっています。
自賠責保険は、被害者の保護と救済を目的とする保険ですから、
被害者に重大な過失(70%以上の過失)があった場合に限って、被害者の過失の程度に応じて
損害額から一定の率が減額されます。
過失相殺による減額は、治療費、休業損害、慰謝料など、その事故で被害者が被ったすべての損害を
対象とするのが普通です。
但し、人身事故ではなく、車同士の車両事故(物損事故)の場合には、「それぞれの損害額」
を、「それぞれの過失割合」にい応じて互いに負担しあうことになります。
無免許での泥酔運転や、50キロ以上の速度オーバーといった常識外の危険な運転が
原因による事故などのように、加害者側に一方的な過失(100%の過失)があるケースを退き、
被害者の過失の程度に応じて、被害者の過失相当分が損害額から減額されます。
つまり、過失相殺されることで、被害者が実際に受け取れる損害賠償額は、
加害者の過失割合分となるのです。
ほとんどの交通事故は、加害者だけではなく、被害者にも事故の発生原因となる何らかの過失が
認められます。こうした場合、加害者だけに損害額を負担させるのは
明らかに不公平です。
「過失相殺」とは、こうした不公平をなくすために、加害者と被害者の過失の程度(過失割合)に応じて、
当事者間で損害賠償責任を負担しあうという制度です。
◆店舗が損壊した為に店舗縮小を余儀なくされた場合
店舗の修理期間中に、事業を休業・縮小する必要があった場合には、
減少した営業利益を請求できるケースもあります。
但し、そのためには営業利益の減少を立証しなければなりません。
◆犬や猫などのペットが死傷した場合
ケガの場合は治療費、死亡した場合はペットショップでの購入価格や、平均的な
販売価格が損害賠償額となります。
家族同然の存在だったとして、裁判で飼い犬の慰謝料を認めた例もあります。
車の衝突や接触などによってモノ(品物)が破損した場合、
所有者はモノの種類や損傷の程度に応じて、加害者に損害賠償を請求できます。
◆建物、看板、塀、玄関などが損壊した場合
車の損傷と同じく、修理が可能な場合には修理費用、修理が不可能な場合
(修理が可能でも修理費用が品物の時価相当額を超える場合を含む)には、
品物の時価相当額が損害賠償額となります。
時価の算出には、その品物の購入価格、新品価格、使用年数、事故前の状況などを
参考にします。
◆休車補償
損壊した車がタクシーやトラックなどの営業車の場合、すぐに代車の用意が出来ずに修理(買換え)
期間中の休業を余儀なくされるケースがあります。
この場合、被害者は休業期間中の減収分を休車補償として加害者に請求できます。
休車補償の基礎となる金額は、その会社の平均売上(事故前少なくとも3ヶ月以上)から
必要経費を差し引いた額とするのが普通です。
損壊した車の修理期間や買換え期間など、被害者が車を使用できなくなった期間に
生じる損害には、「代車使用量」「休車補償」の2つがあります。
◆代車使用料
修理期間中、または買換え車両が搬入されるまでの間に、被害者がレンタカーなどの代車を
使用した場合、その代車使用料を加害者に請求できます。
但し、日々の通勤の足や営業車としての使用など、代車が無ければ日常生活に支障がでるケース
に限られます。
代車使用料は、原則として損壊した車と同クラスのレンタカー使用料となります。
◆修理が可能なケース
修理工場の見積もりを基に、修理費用の全額を加害者に請求できます。
修理しても機能的障害が残ったような場合には、
「評価損(格落ち)」として修理費用の2~3割程度を請求できるケースもあります。
修理可能な場合でも、事故直前の車の評価額を修理費用が上回る場合には、
全損と同じ扱いになってしまいます。
事故で車が尊称した場合、修理不可能なケースと修理可能なケースが出てきます。
事故の原因がすべて相手にあるような場合には、被害者はその損害分をすべて加害者に
請求することができます。
◆修理が不可能なケース(全損)
事故直前の車の時価相当額(評価額)が損害賠償額になります。
買換え時の登録手数料なども、合わせて請求可能です。
被害車両がまったくの新車だった場合は、購入価格がそのまま評価額となりますが、
通常は中古車市場での同等の車(車種・年式・肩・使用状態など)の売買価格などを参考に
評価額を算定します。
中古車が全損しても、新車への買換え費用は請求できません。
物損事故の場合、人身事故と異なり、自賠責保険や任意保険等による賠償方法に制限があります。
こうした違いがあるために、加害者側が非を認めない場合には、
示談交渉が難航するケースが多々あります。
また、事故時には単なる物損事故だと思っていても、時間の経過と共に予期しなかった
人身損害が出ないとは言い切れません。
それだけに、たとえ軽微な物損事故でも、人身事故と同じように警察への通報や保険会社への
報告を怠らないようにしてください。
物損事故とは、人間の身体には損害が無く、車や建物などに対して損害を与えた事故のことです。
物損事故と人身事故とでは、次のような大きな違いがあります。
①自賠責保険からは保険金が支払われない
(自動車損害賠償保障法が適用されないため)
②物損事故の損害賠償は、加害者本人に請求することが原則ですが、
加害者が加入している任意保険会社が示談代行する場合には、
保険会社に請求する
③加害者の違法行為・故意・過失によって損害が生じたことを被害者側が
証明しなければならない
④それぞれの損害額をそれぞれの過失割合に応じて互いに負担しあうことになる
事故による後遺症と認められれば、最初の請求分と、既に受け取った損害賠償額・保険金との差額が
被害者に支払われます。後遺症について触れられていない示談では、
後遺症と交通事故との因果関係を明らかにする必要があるため、
事故後の経過時間が長いほど、その証明は難しくなります。
既に示談書が取り交わされていても、示談時には予期しなかった後遺症が出てきたときには、
被害者は後遺症の損害賠償を加害者に請求することが可能です。
示談で後遺症について触れなかった場合には、次のような方法で後遺症の損害を請求することができます。
①後遺症の原因が事故による可能性が高い時は、事故時の状況、事故後の状態など、
事故当時から現在までの詳細を医師に話、事故による後遺症かどうかを検討してもらう
②医師の診断書で事故との因果関係が明らかになったら、加害者に損害賠償を請求する
むち打ち症は、後遺障害別等級表では、7級、9級、12級、14級の「神経系統の機能」「神経症状」
という項に入ります。
但し、神経症状の為にレントゲンにも映らないなど、
他覚的な所見が無い自覚症状だけのケースが多いため、
後遺症として認められにくいのが実情です。
後遺症として認められる場合でも、通常は12級が14級の場合が
多いようです。
自動車事故の被害者が、むち打ち症で苦しむケースは少なくありません。
「むちうち症」とは、車で追突されたときなどに、首や背中に急激なショックが加わり、
首が前後にムチのようにしなることが原因で生じる
首や肩の痛みのことです。
一般的には「頸椎捻挫」と診断されます。
後遺障害別等級表に「むち打ち症」という言葉は出ていませんが、後遺症として損害がみとめられない
わけではありません。頸部への瞬間的なショックが原因で、被害者が痺れ、めまい、
吐き気、頭痛、肩こり、脱力感など、さまざまな神経症状を覚えるのは事実だからです。
◆自賠責基準の慰謝料
「後遺障害別等級表」で定められている保険金額には、
後遺症による逸失利益と慰謝料が含まれています。
◆日弁連基準の慰謝料
後遺症の等級に応じて定額化されています。
被害者が実際に請求する慰謝料の額は、この基準を参考に算定し、
状況によっては増額することも可能です。
また、重度の障害で介護の必要がある場合などには、
本人分とは別に、本人分の2~3割の慰謝料が近親者に認められることもあります。
後遺症の慰謝料は、被害者の年齢、性別、職業、症状などの要素を十分に考慮して算出されます。
例えば、顔に残った傷跡は同程度でも、高齢の男性と若い女性の場合などでは、
被害者が受ける精神的ダメージも大きく異なってくるからです。
しかし、慰謝料を算定するためには、何らかの基準が必要です。
そこで傷害事故の慰謝料と同じように、
後遺症の慰謝料も等級に応じて定額化されています。
後遺症による逸失利益は、「①基礎収入×②労働能力の喪失率×③労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数または新ホフマン係数」で算出します。
①基礎収入:原則として事故の前年の収入
②労働能力喪失率:「後遺障害別等級表」の労働能力喪失率を参考とした減収の割合
③労働能力喪失期間に応じた中間利息を控除する:被害者の症状固定時の年齢から減収になる期間を出す。
将来の減収分を一括請求するため、その期間に対応するライプニッツ係数または新ホフマン係数を乗じて
中間利息を控除した減収分を計算する。
後遺障害と認定された被害者は、治療期間中に認められていた「休業損害」がなくなる代わりに、
それ以降は将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺症による「逸失利益」を
加害者に請求することになります。
後遺症が残った場合、事故前と同じように働けないケースが多いためです。
〇家屋・自動車などの改造費
後遺症の程度に応じて、家の出入り口、風呂場、トイレなどの改造費、自動車の改造費
などの実費を請求できる
〇装具などの購入費
後遺症の程度によっては、義足、車いす、補聴器、義眼など、
日常生活を送るうえで必要とされる装具などの購入費を実費で請求できる。
それらの装具は半永久的に使用できるものが少ないため、
交換・買換えの必要が認められるものについては、
その費用全額を請求できる。
〇将来の治療費、付添看護費など
原則として認められないが、症状固定後であっても、症状の内容、程度、治療内容
などにより、症状の悪化を防ぐなどの必要性が認められれば、その費用を請求できる。
被害者が寝たきりなどの状態で、常に介護が必要な場合には、原則として平均寿命
迄の間、将来の付添看護費を請求できる。
後遺障害の等級認定は、ほとんどのケースが書類審査だけなので、
後遺障害診断書には具体的な症状を記入してもらうことが必要です。
医師に症状をはっきり伝えるためにも、自分の症状が何級の
後遺障害に当てはまるのか、後遺障害等級表で事前に確認しておくとよいでしょう。
後遺障害かどうかを判断してもらうためには、まずはじめに医師の診断を受け、
「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。この診断書の内容によって、
その症状が後遺障害別等級表の何級に該当するのかが判断されます。
自賠責保険では、傷害保険金とは別に「後遺障害別等級表」の等級に応じて、
後遺障害保険金を支払うことになっています。
これに準じて、傷害による損害と後遺障害による損害を別に算定するのが普通です。
一通りの治療が終わり、医師から症状固定と判断された時点で、傷害から後遺障害の
損害賠償に移行します。
後遺障害(後遺症)とは、事故による失明、半身不随といった重度の障害や、
関節の変形など、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と
判断された身体的な障害のことです。
「慰謝料」は事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償額です。
傷害事故の場合、ケガをして入院・通院した被害者は、加害者に対して慰謝料を請求できます。
傷害事故の慰謝料の額は、入院・通院の期間、ケガの状態などで定額化されています。
◆自賠責基準の慰謝料
「実際に治療を受けた日」を2倍にした日数か、「治療期間」の日数のいずれか少ない方の
日数に対し、1日につき4200円(定額)の慰謝料が認められます。
◆日弁連基準の慰謝料
入院期間と通院期間によって定額化されています。一般的に自賠責基準の慰謝料より高めに
設定されています。
失業者や学生、アルバイトの場合は、原則として休業損害を請求することはできません。
但し、状況によっては、次のような方法で休業損害を請求することができます。
〇学生や失業中で、就職が具体的に決まっていた人の場合
就職予定日から、実際に就職先で働くまでの入院・通院期間について、
就職予定先で得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。
〇アルバイトやパートタイマーで、就労期間が長く、収入の確実性が高い人の場合
一年以上など、同じアルバイト先やパート先で継続して働いていた場合には、
正社員と同じく、事故前3ヶ月間の収入に基づき、休業損害を請求できます。
個人事業主(事業所得者)や、医師・税理士・著述業などの自由業者の場合は、
原則として事故前年の年収に基づき、休業損害の請求額を計算します。
事故前年度の所得税申告所得額(年収)を1年の日数である「365日」で割れば、
1日当たりの収入を算出できるからです。
申告所得額が実収入よりも少ない場合には、
領収書・帳簿・源泉徴収票などによって実収入額を確実に証明できれば、
その額を年収額とすることもできます。
専業主婦の場合は、「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金に基づき、
休業損害の請求額を計算します。
実際に収入が無くても、家事休業分の損害として請求できます。
パートタイムや正社員など、仕事を持つ主婦の場合には、仕事と家事労働を兼業しているケースが
ほとんどです。この場合は、仕事と家事の両方を二重に請求することはできません。
「現実の収入」と「賃金センサスの女子全年齢平均賃金」のいずれか多い方の額を
請求することになります。
参考文献:
「交通事故」完全対応マニュアル 鈴木清明著
わかりやすい交通事故 吉田杉明著
